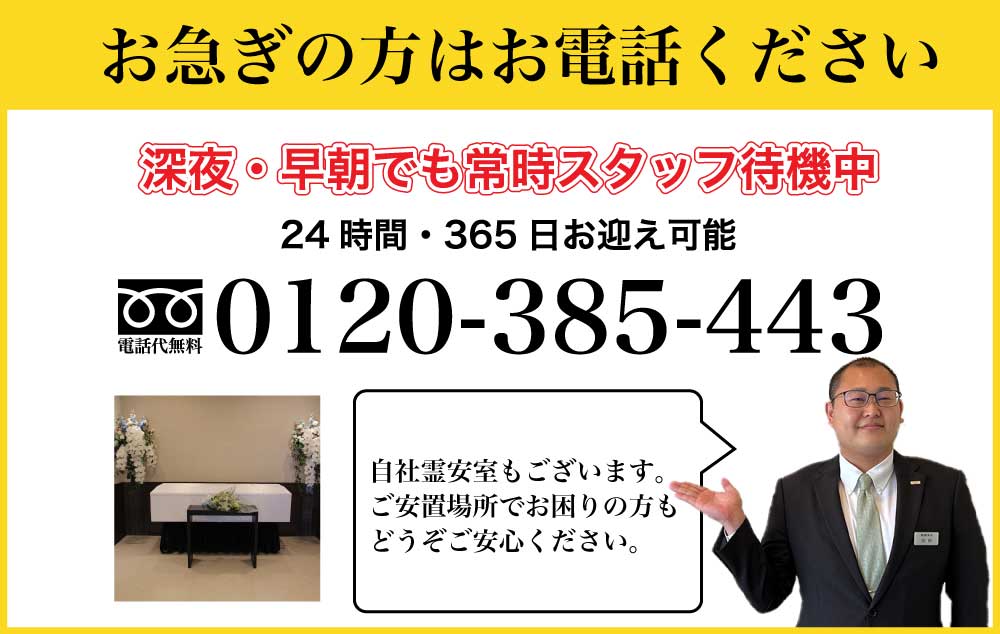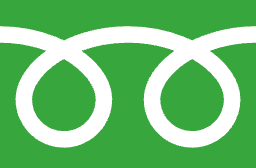こんにちは、八王子市・日野市・世田谷区で安心のご葬儀・家族葬のお手伝いをする葬儀社、都典礼(みやこてんれい)です。
今日もご葬儀に関する疑問、悩みの解消に役立つ情報をお伝えします。
大切な人との別れは必ず訪れます。残された遺族は悲しみをこらえながら、故人と別れるため、葬式を行います。
しかし悲しみに暮れながらご葬儀を終えて、一安心とはいきません。故人の残したものを受け継ぐために、相続の手続きを行い、場合によっては相続税を支払わなくてはなりません。
相続税は税金であるため、控除を受けることができ、ご葬儀費用も対象となるものがあります。
そこで今回は相続の際に相続税がかかる場合や、相続税控除の対象となるご葬儀費用について紹介します。
相続と相続税
相続は人が亡くなったときにその人の財産を家族など、特定の人が引き継ぐことを言います。
例えば父親が亡くなった時は、配偶者と子どもが相続するのが一般的です。
相続というと受け継いだ財産全てに相続税がかかるものだと思われがちですが、相続する財産の総額によっては相続税はかかりません。
では、相続税はどのようなときに発生するのでしょうか。
相続税について簡単に見ていきましょう。
相続税とは
相続税は財産を相続した人にかかる税金ではありますが、全ての財産に税金がかかるとは限りません。
相続する財産から非課税の財産やご葬儀費用などを差し引いた残りの額にかかるのが相続税です。
相続税には控除があり、控除を受けた残りの額に対して税金がかかります。
その計算式がこちらです。
遺産にかかる基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人数
仮に相続人が一人の場合の基礎控除は3,600万円となるため、3,600万円までの遺産額には相続税はかかりません。
このように、相続税は相続する遺産総額によって、かかるかかからないかが決まります。
ご葬儀費用とは
ご葬儀には式場使用料やスタッフ人件費、火葬費などさまざまな費用がかかります。
その他にも宗教関係者などへの謝礼などもご葬儀費用に入るとともに、費用を支払う方法によって控除が受けられるかが決まります。
また、ご葬儀費用を支払うのは一般的には喪主ですが、費用を支払う人は法律で決まっていません。
そのため親族や友人であったとしても、支払うことはできるのです。
ご葬儀費用は項目によっては相続税の控除対象のものもあります。控除できるものとできないものについてみていきましょう。
相続税控除の対象となるご葬儀費用
相続税控除を受けることができるのは、ご葬儀費用を支払った人物のみのため、支払っていない人は受けることができません。
例えば父親のご葬儀で相続人である母親が全額ご葬儀費用を支払った場合、母親のみが控除を受けることができ、子どもたちは受けられません。
ご葬儀費用で控除ができるものは、ご葬儀に直接かかる費用と決められており、下記のものが該当します。
- 遺体の搬送費用
- お布施などの宗教者へのお礼の費用
- ご葬儀前後に生じた費用
- 納骨費用
特にご葬儀前後に生じた費用も対象となるため、領収書や支払い記録などはしっかりと保管しましょう。
相続税控除対象外の費用
ご葬儀費用の対象となるものは、ご葬儀費用として本当に必要な費用のみであり、直接的に関係のない費用は相続税控除対象外となります。
当てはまる費用をいくつかあげます。
- 香典返し
- 位牌・仏壇などの購入費用
- 初七日以降の法事費用
上記のように直接ご葬儀とは関係のない費用は、全て控除対象外です。
ご葬儀費用控除を受ける際の注意点
ご葬儀費用の控除を受けるためには、いくつか注意点があります。
主な注意点を3つあげますのでみていきましょう。
ご葬儀費用は確定申告対象外
遺産は所得に含まれないことから、確定申告で控除を受けることはできません。
ご葬儀費用は相続税のみ控除されるため、確定申告も同じだと思わないようにしましょう。
申告時は領収書などを持参する
ご葬儀費用の申告を受ける際は、どのようなご葬儀で支払いをしたのかを明確にするために、領収書を持っていく必要があります。
そのためご葬儀に関わるものは領収書をとっておくようにしましょう。
また、領収書を出してもらえなかった時のために、支払い記録を作成しておくことも重要となります。
相続税の申告・納税の期間
相続税の申告や納税には期間があり、故人がなくなった翌日から10カ月以内という決まりがあります。
この期間内に行わないと罰則があるため、注意が必要です。
さらに遺産に修正がある場合、修正申告書を提出する必要があるため、そちらも合わせて注意しましょう。
申告の手続きに不安がある場合は、税理士に相談することをおすすめします。
まとめ
故人がなくなったときに発生する遺産相続は、その額次第では相続税の対象となります。
しかし、ご葬儀費用は内容によって控除を受けることができるほか、相続税にも基礎控除があります。
相続税の対象か気になるときは、専門家に依頼するなどし、正しく申告を行いましょう。